
家計簿って面倒くさいし、つけている効果がいまいちわからない
そう感じていませんか?
「貯金できる人」と「できない人」の差は、実は家計簿にあります。
月9万円超の削減に成功した筆者が、家計簿の始め方と続けるコツについてご紹介します。
家計簿の始め方や、あなたにぴったりの家計簿の選び方がわかります。



今日から家計管理をラクにして、貯金ゼロから抜け出しましょう!
1. 家計簿にも意味がある。家計簿をつける目的とメリットを理解しよう
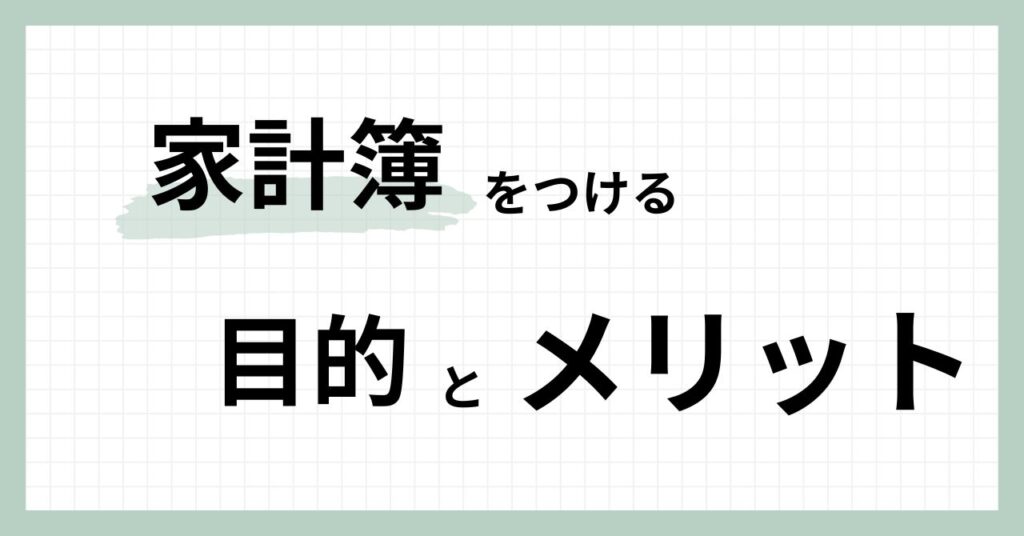
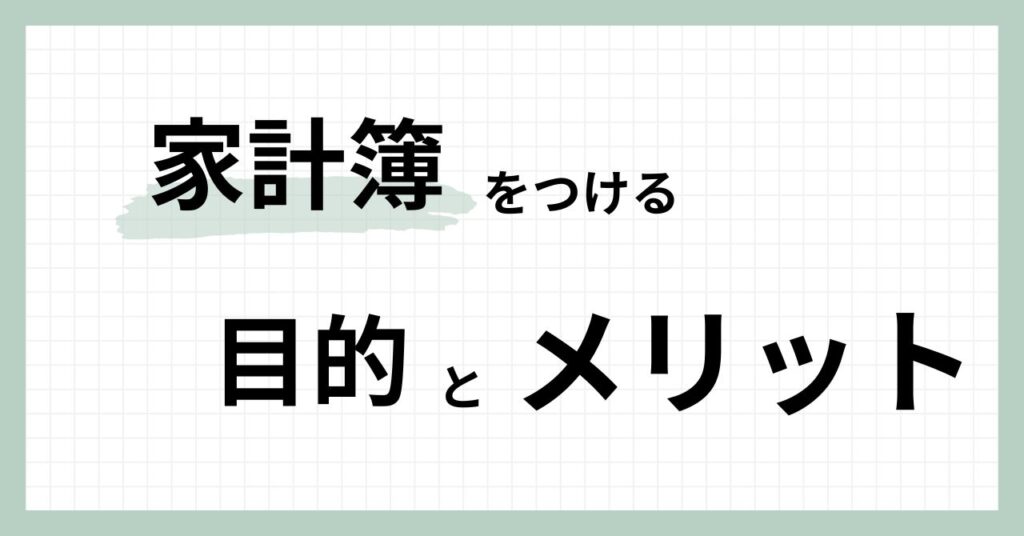
家計簿をつける最大の目的は、家計のお金の流れを「見える化」することです。
「見える化」によって、3つの大きなメリットが得られます。
メリット1:収入と支出を明確に把握し、家計の全体像が「見える化」できる
あなたは毎月、何にどれくらいお金を使っているか正確に答えられますか?
家計簿を始める前は、入ってきた給料がいつの間にか空っぽ。
そのため、「何にいくら使っているのか?」がわからない状態でした。
実際に記録してみると、解約し忘れのサブスクや高額なスマホ代。
ついついコンビニで買うスイーツなどが積み重なり、お金がない状態だとわかりました。
このように、自身の収入と日々の支出を記録することで、月々の家計が黒字か赤字か、そしてどこにどれだけお金を使っているのかがひと目でわかるようになります。
支出の傾向や家計の実態が見えてくると、自然と節約ポイントや、月にどのくらい貯金できるのかが明確になります。
メリット2:お金の使い方を「改善する」作戦を立てられる
お金の流れが「見える化」されると、自身の支出の癖や、無駄な出費に気づくことができます。
例えば、「洋服を買いすぎている」など、今まで気づかなかった無駄が明らかになります。
そうすることで、「新しい服を買う前に、本当に必要か考えよう」と考えるようになります。
欲に任せた買い物ではなく、考えるようになると無駄遣いが抑えられ節約を意識できるようになります。
家計簿は、お金の使い方を考え、より良い行動へ繋げるための強力なツールなのです。
メリット3:貯蓄や目標達成へのモチベーションになる
家計簿は、具体的な貯蓄目標を立てる上で欠かせません。
旅行資金、マイホーム購入、老後資金など、目標額と期限を設定することで、月々に貯めるべき金額が明確になります。
家計簿を続けるうちに、無駄な支出が減り、毎月お金が増えていくことが実感できます。
小さな成功体験が、大きな目標達成へのモチベーションにつながります。
「今月は目標額をクリアできた!」という達成感は、家計簿を楽しく続けるための大きな原動力になるでしょう。
2. 家計簿は種類が多い!タイプ別メリット・デメリットを比較
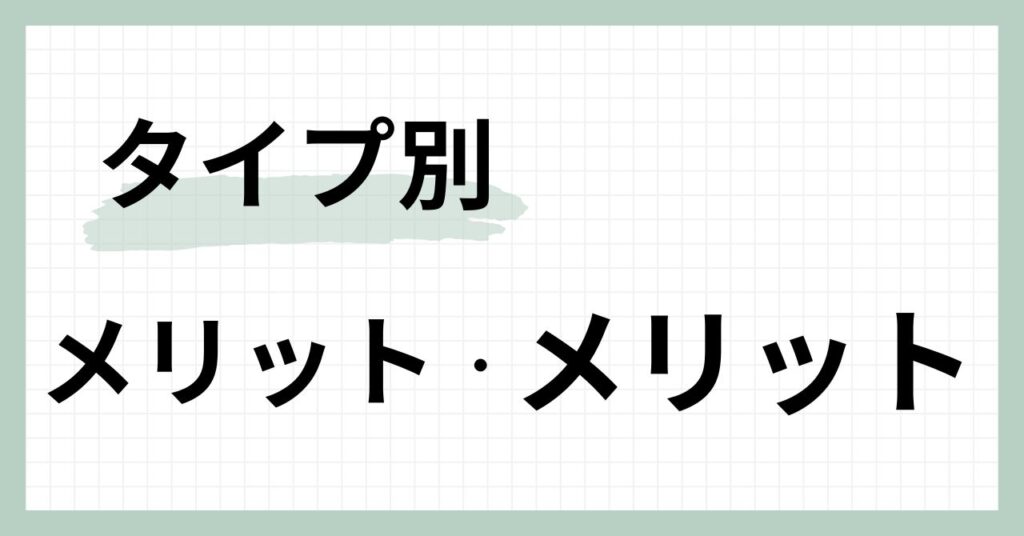
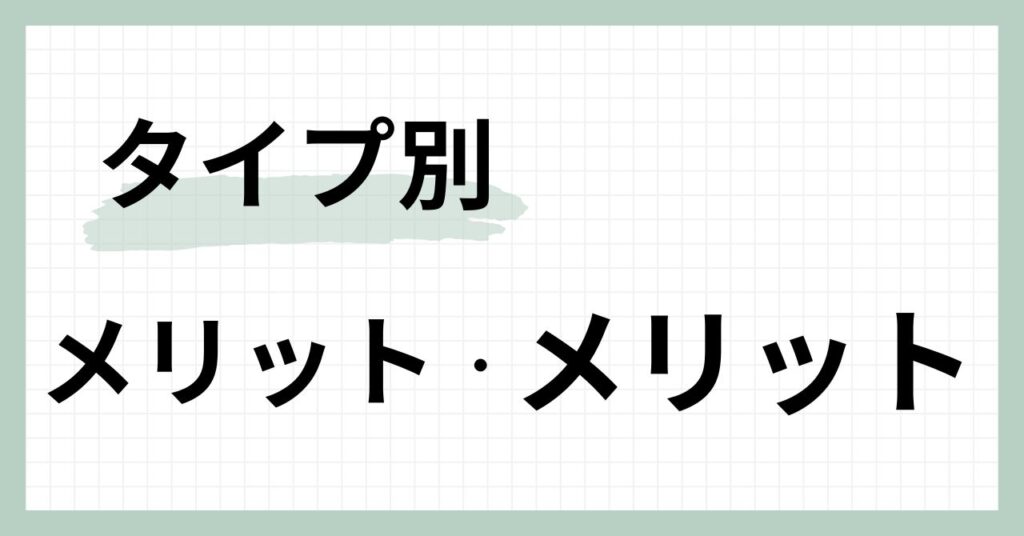
家計簿には、主に「手書き」「アプリ」「表計算ソフト」の3つのタイプがあります。どれを選ぶかで、使いやすさや続けやすさが大きく変わります。それぞれの特徴を確認して、あなたの性格やライフスタイルにぴったりの家計簿を見つけましょう。
手書き家計簿(ノートタイプ)
昔から定番の家計簿で、市販の家計簿やノート、もしくは自分好みのフォーマットを作成し、使用するタイプです。
- メリット:
- お金の流れを強く意識しやすい: 自分でペンを動かして書くため、お金の流れがわかるようになる。「何にいくら使ったか」が明確になる。
- 達成感がある: 月の集計が終わったノートを見ると、「これだけ頑張った!」という達成感があり、モチベーション維持につながる。
- 自由にカスタマイズできる: 費目やレイアウトを自由に設定でき、メモや感想も書き込みやすい。
- デメリット:
- 記入に手間と時間がかかる: 毎日まとめて記入する時間がないと、レシートがたまってしまいがち。
- 手動で計算が必要なため、金額の相違が出る可能性が高い: 計算ミスや転記ミスが起こりやすい。こんな人にオススメ
- 書くことが好きな人
- 時間に余裕がある人
- 手帳やノートなどが好きな人
- 計算が早い人(電卓でもOK)
家計簿アプリ
スマートフォンやタブレットで利用できるデジタルツールです。
手軽に利用できることから人気が高まっています。
- メリット:
- 自動集計・自動記録で利便性が高い: 銀行口座やクレジットカードと連携すれば、利用履歴が自動で家計簿に反映される。
- レシートを撮影するだけで自動入力してくれるものもあり、手間が大幅に削減できる。
- 手間が少なく長く続きやすい: 手軽に入力できるため、家計簿が苦手な人でも習慣化しやすい。
- グラフで推移を比較しやすい: 収支や費目の推移を自動でグラフ化してくれるため、お金の使い方の変化が一目で分かる。
- デメリット:
- 見直しする習慣がないとお金への意識が薄れがちになる: 便利さゆえに、ただ記録するだけで満足してしまい、振り返りを怠ってしまう可能性がある。
- 操作に慣れが必要: アプリによっては多機能すぎて、使いこなすまでに時間がかかることがある。こんな人にオススメ
- 時間があまりない人
- フォーマットを考えることが面倒な人
- クレジット払いなどの電子決済が多い人
表計算ソフト(Excelなど)
パソコンでの作業に慣れている方におすすめの家計簿です。
- メリット:
- 入力・集計・分析が簡単: 一度関数を設定すれば、自動で集計やグラフ化ができる。
- テンプレートが豊富: ウェブ上で無料で公開されているテンプレートを利用すれば、自分で一から作る手間を省ける。
- デメリット:
- パソコンが必要: スマホで手軽に記入したい人には向いていません。
- 関数ミスがあっても気づきにくい: 関数の設定が複雑だと、計算ミスがあった場合に発見しにくい。
こんな人にオススメ
PC作業に慣れている人
数式に抵抗がない人
3. 自分に合った家計簿の選び方と継続するコツを紹介
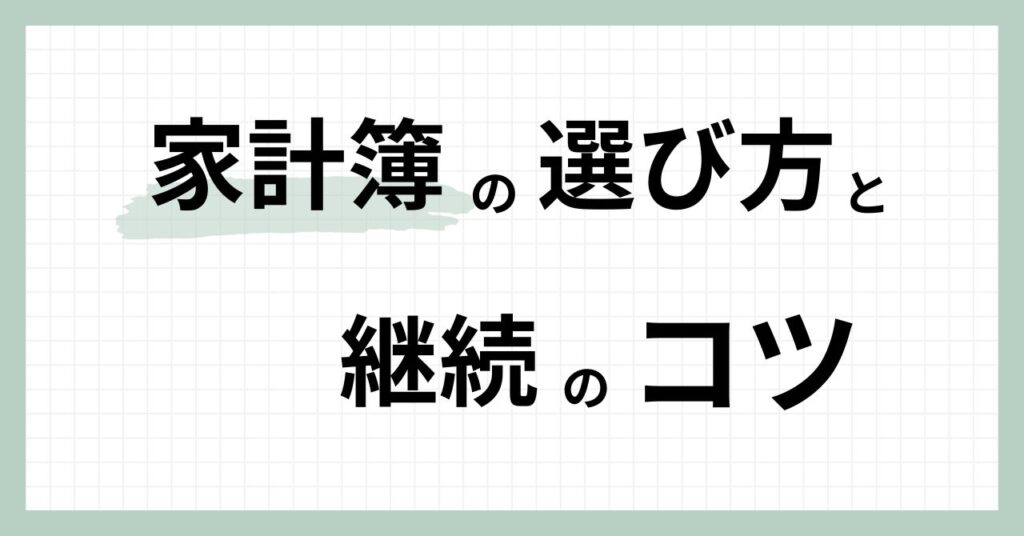
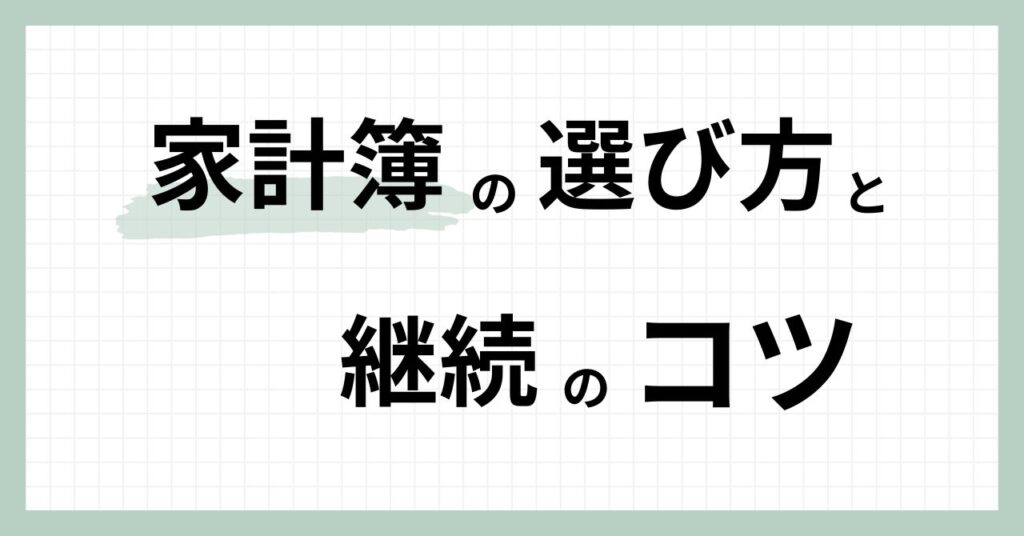
家計簿には色々な種類があります。そのため、自分に合わないものももちろんあります。
合わないものを選んでしまった場合、家計簿を続けることが難しくなります。
家計簿は続けることに意味があります。
習慣化しやすい、自分に合ったものを取り入れましょう。
1. 目的と目標を明確にする
家計簿を始める前に、「何のために家計簿をつけるのか」という目的と目標を具体的に設定しましょう。
例えば、「3年後にハワイ旅行に行くために、月々2万円貯金する」など、具体的な数値を入れます。
そうすることでやるべきことが明確になり、モチベーションが維持されます。
2. 費目を増やしすぎない
最初から細かく分類しすぎると、何に分類すれば良いか分からなくなり、面倒に感じる原因になります。
まずは「食費」「固定費」「変動費」など、少ない項目から始めるのがおすすめです。慣れてきたら、少しずつ項目を追加していきましょう。
3. 完璧を目指さない
「数字が合わないから、もう家計簿は続けられない」と挫折してしまう場合があります。
しかし、家計簿は初めから完璧である必要はありません。
慣れるまでは多少の誤差や記入もれは気にせず「おおらかな気持ち」で取り組むことが大切です。
4. ルーティン化する
家計簿を習慣にするためには、決まったタイミングで記入すると定着しやすくなります。
「毎週日曜日の夜に1週間分をまとめて記入する」「買い物の後、すぐに入力する」など、自分のライフスタイルに合ったタイミングを決め、ルーティン化しましょう。
5. 関連グッズをひとまとめにする
レシート、電卓、筆記用具などを一か所にまとめておくと、スムーズに作業を始められます。お気に入りのノートやペンを揃えるなど、気分が上がる工夫をすることも大切です。
まとめ
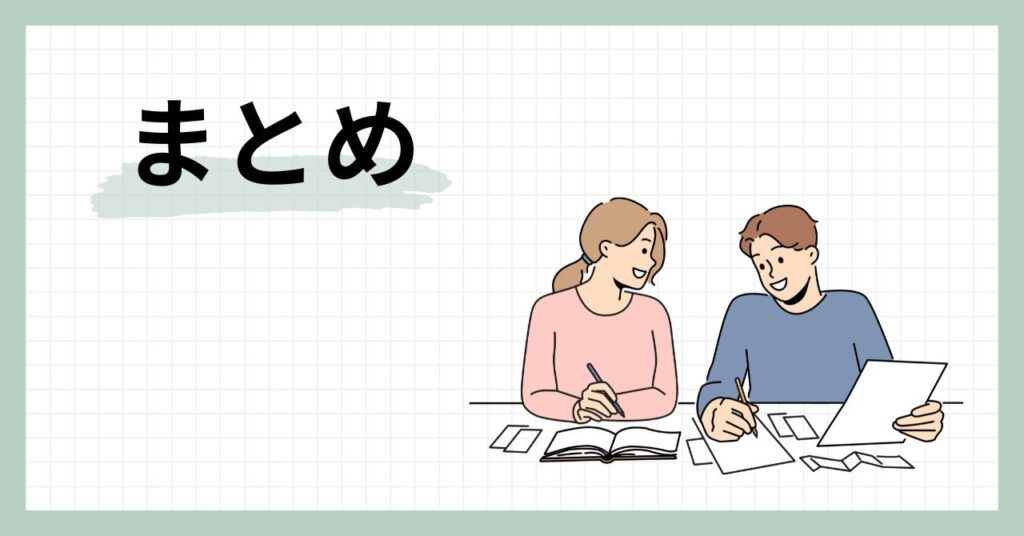
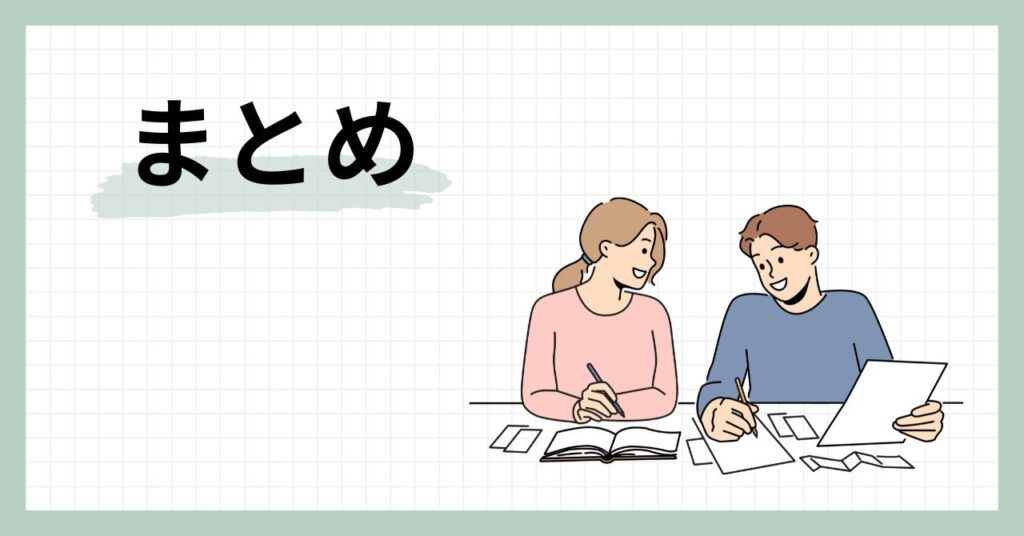
家計簿は、最初から完璧を目指すのではなく、自分に合った方法で「お金の見える化」から始めることが大切です。
継続することで、家計管理があなたの生活の一部となり、目標達成への道が開かれます。ぜひ今日から、家計簿をあなたの「強い味方」にしてください

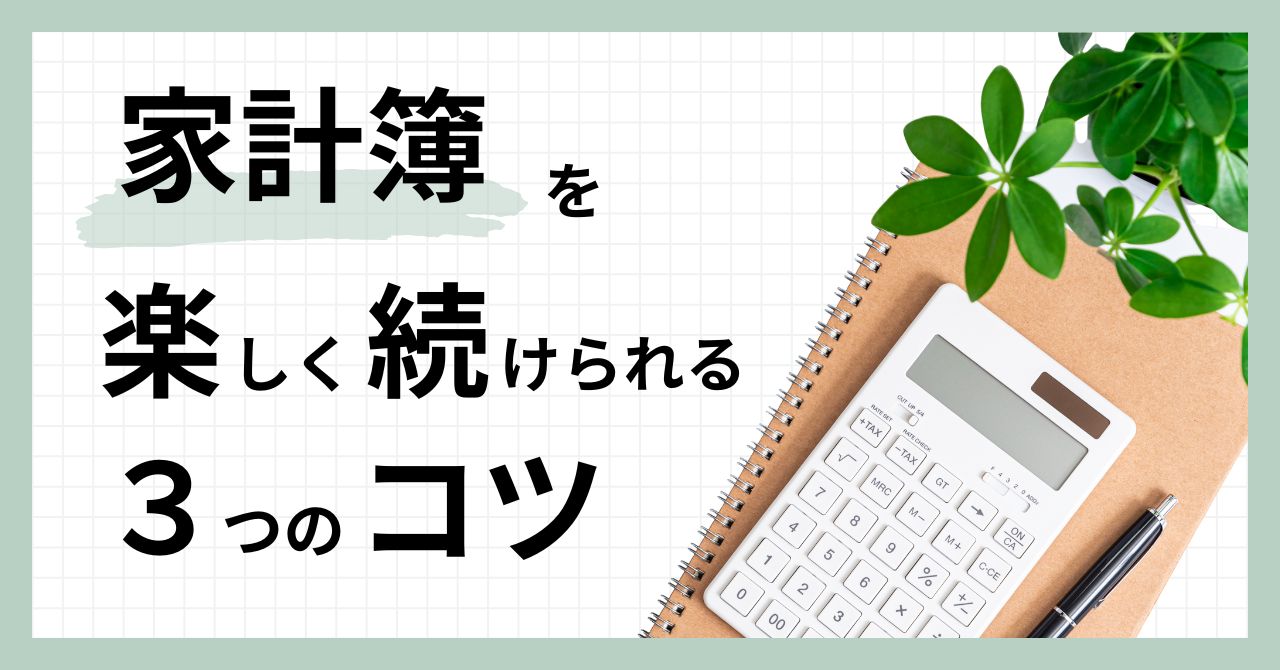


コメント